心療内科や精神科・メンタルクリニックを受診しようと思っているけれど、どうやって選んだらいいかわからない…。
初めての受診だと、不安になりますよね。
そこで、実際にどのような基準でクリニックを選んだか、初診ではどのようなことをしたのか、筆者の体験談をまとめました。
こうしておいて良かった!
逆に、こうすれば良かった…
といったことも書いてあるので、参考にしていただければと思います。
筆者は医療従事者ではございません。この記事は、「受診する側」としての目線で書いたものであることをご承知おきください。
メンタルクリニックを選んだ基準
私が受診したときに確認したポイントは、以下のとおりです。
- 通いやすい立地
- 予約が取りやすい
- 診断書を初診日に発行してくれる
- 医師やカウンセラーが複数名在籍している
それぞれ詳しく見ていきますね。
①通いやすい立地
メンタルクリニックは定期的に通院が必要なことが多いため、「通いやすい立地」というのが大事です。
行くのが大変だと、通わなくなってしまうこともあります。
自己判断で通院を止めてしまうと、症状が長期化してもっとつらくなってしまうかもしれません。
私は最寄り駅から電車1本・駅から徒歩5分以内にあるクリニックを選びました。
②予約が取りやすい
基本的に、メンタルクリニックは予約が取りにくいです。
人気のところであれば、1ヶ月先まで埋まっているということもよくあります。
でも、受診を決めた以上は早く診て貰いたいですよね。
ネットで検索するときに、
といった記載があるところを探すとよいです。
③診断書を初診日に発行してくれる
休職を考えている方であれば、特に重要なのが「診断書の発行」です。
発行できるタイミングはクリニックによって異なるようです。
ウェブサイトに発行までの目安を記載してあるクリニックが多いので、事前に確認しておくことをオススメします。
できるだけ早く休職をしたいのであれば、診断書の当日発行が可能なクリニックを探すとよいでしょう。
診断書の発行を希望する場合、自分から医師に「診断書が欲しい」と伝える必要があります。また、発行は医師の判断によるため、希望すれば必ず発行されるというわけではないです。
④医師やカウンセラーが複数名在籍している
心の悩みを相談するうえで、医師やカウンセラーとの相性は重要です。
複数名在籍しているところであれば、
「この先生、あまり合わないかも…」
と思ったときは、申し出れば担当を変更してもらえる可能性があります。
もともと医師が一人しかいないところだと、合わなかった場合クリニック自体を変えなければならなくなります。
インターネットの口コミなどを参考に、そのクリニックの医師がどのような人柄か下調べをしておくのもひとつの方法です。
また、カウンセリングの希望がある場合は、クリニックにカウンセラーが在籍しているかも確認しておきましょう。
いない場合はクリニックとは別で、カウンセリングを行っている施設を探すことになります。
筆者が実際に行ったメンタルクリニックについて
筆者はゆうメンタルクリニックに行きました。
「マンガで分かる心療内科」
という本で有名なクリニックです。
このゆうメンタルクリニックは、さきほどご紹介した選び方の基準のうち、3つを満たしています。
- 予約が取りやすい
- 診断書を初診日に発行してくれる
- 医師やカウンセラーが複数名在籍している
私は立地的にも通いやすかったので、このクリニックを選びました。
すべての院が最寄り駅から徒歩5分以内なので、自宅からの電車のアクセスが良ければ通いやすいと思います。
関東エリアに10院、関西・東海エリアに5院あるとのことです。(2026年1月現在)
※クリニックの最新情報については、「ゆうメンタルクリニック」の公式サイトでご確認お願いします。
予約~受診当日の流れ
こちらに記載するのは、筆者が受診した「ゆうメンタルクリニック」での場合です。
実際の流れは受診するクリニックによって大きく異なると思いますので、一例としてお読みください。
また、同じ「ゆうメンタルクリニック」であった場合でも、どこの院かや症状によって流れが違う可能性もあります。
ホームページで予約、問診表の入力
クリニックのホームページでネット予約ができました。
予約完了後、続けて問診表の入力が可能でした。
入力は任意ですが、ここで入れておくと当日問診表を書かなくて済むので、院内での待ち時間を短縮できます。
私が実際に入力したときの回答時間は、15分くらいでした。
項目が多いため、事前に済ませたほうが気持ちに余裕をもって入力できるのもメリットです。
診察中の様子
診察室では、医師のほかに医療秘書が同席していました。
医療秘書は医師に代わって、患者さんの話を聞きながらその場で電子カルテを作成してくれます
そのため医師はパソコン操作をする必要がなく、こちらにしっかりと顔を向けて話してくれるという点は好感が持てました。
医師に症状や悩みについて説明していくのですが、このとき思ったことがあります。
理由はどちらも同じで、診察時間が約10分と短いからです。
その場で考えながら話していると、何を話すか忘れてしまったり、大事なことを伝え漏れてしまったりする可能性があります。
問診表にしっかりと回答していれば、医師はそれをもとに診察をしてくれますので、説明の抜け漏れがあっても心配ありません。
診察室で説明するときも、メモを持っていけばそれを見ながら話せますし、医師の話を書き留めておきたいと思った時メモに書き込むこともできます。
【メモにまとめておくと良い情報】
・いつから症状が出始めたか、継続している期間はどのくらいか
・その症状によってどのようなことに困っているか、生活に支障が出ているか
・現在の生活リズム(眠れているか、食事は3食とれているか など)
診察後の採血と心理検査
診察が終わったあと、採血と心理検査を2つ行いました。
「メンタルの不調なのに採血?」
と疑問に思いましたが、院内に採血をする理由について書かれた掲示物がありました。
以下、掲示物の内容を簡単にまとめました。
採血
身体的な要因が、精神症状をひきおこすことがあるため
貧血や甲状腺の異常などの身体的な問題がある場合も、抑うつ症状が出ることがあるそうです。
適切な処置や投薬を行うことにより、精神症状も改善するため、見極めのために血液検査を行っているとのことでした。
処方する薬の種類や量を判断するため
血液の状態をみて、処方する薬がきちんと効果が出るか、投薬しても問題ないかを調べているそうです。
心理検査(CES-D検査、バウムテスト)
CES-D(セスデー)検査
自己評価形式になっているテストです。
2回目以降の診察時に検査結果を渡されたのですが、そちらには「抑うつ状態について客観的に把握するための心理検査」と書かれていました。
たとえば、「よく眠れない」といった設問に対し、
- 眠れない日はなかった(1日未満)
- 少し眠れなかった(1~2日)
- しばしば眠れなかった(3~4日)
- ほとんど眠れなかった(5~7日)
というような回答項目があり、その症状がどの程度の日数起こっていたかを選択していきます。
この回答を数値化して60点満点とし、合計点が16点以上の場合、抑うつ状態と考えられるとのことです。
所要時間10分程度と簡単に回答できますが、なんと精度は90%と記載されていました。
ちなみに、私は24点で軽度抑うつ状態と結果が出ました。
ですが、実際はこの検査内容だけで診断が下されるわけではないです。
医師の診察など総合的に診た結果、最終的に私は「中程度の抑うつ状態」という診断がされました。
検査結果については、あくまで参考とのことです。
バウムテスト
木の絵を描く心理テストです。
「木の形状から、その人の思考や性格のパターンを読み解く」というのが目的だそうです。
私がこのテストを受けた際の、結果の一例を載せておきます。
- 葉の形状から、コミュニケーションスキルが比較的高く、人間関係を作ることが上手い傾向にあると考えられます。ただ、そのために相手に気を使ってストレスに感じている可能性があります。
- 幹の形状から、現状をかなりの努力をして耐えていることが推察されます。
- 枝の形状からストレスをためこみやすいことが考えられます。爆発してしまう前に、なるべく小出しにしたほうが良いかもしれません。
このように、「大まかな性格の傾向」や「現在の精神状態の分析結果」を教えてもらえます。
これを見たとき、「思いのほか当たっているな」と私は感じました。
自分の考え方のクセを、客観的かつシンプルに分析・言語化してもらえるため理解しやすいです。
バウムテストを実施するクリニックの受診を検討している場合は、事前に詳しく調べすぎないようにしましょう。
内容を知っていると、診断結果に影響を及ぼす可能性があります。
受診して初めてわかったこと
ここからは、実際にメンタルクリニックを受診するまで知らなかったこと、思い込みや誤解があったことについて書いていきます。
医師とカウンセラーの違い
心療内科や精神科へ行った体験談を読んでいると、
「先生は全然話を聞いてくれなかった…」
といった意見をよく見かけます。
実際の診察も約10分ほどだったので、たしかに短いなと感じました。
クリニックによっては初診は30分以上たっぷり時間をかけることもあるようですが、2回目以降は早ければ5分くらいで終わることもあります。
「何に悩んでいるか深く理解しなければ診察できないのでは?」
「どうしてそんなに早いの?」
と、疑問に思いますよね。
私も不思議に思っていました。
これは受診するまで知らなかったことなのですが、
悩みをじっくり聞くのはカウンセラー(心理士)が行うため、医師の診察時間は短い
というのが一般的なようです。
私は医師の診察とカウンセリング両方受けていますが、医師からは主に体調の変化・行動面について聞かれます。
(例:朝スムーズに起きられるか、食事は3食とれているかなど)
逆にカウンセリングのときに「胃が痛い」などの体調面の話をすると、
「医師の診察のときに話してみてくださいね」
と言われることがあります。
精神科医とカウンセラーの違いをあらかじめ知っておけば、「医師が話を聞いてくれない」と感じて傷つかなくて済むかな、と思ったのでここに書いておくことにしました。
もし、医師がゆっくり話を聞いてくれないことがつらいようであれば、カウンセリングを検討してみるのも良いと思います。
カウンセリングは基本的に保険適用外なので、その点も考慮に入れて検討することをおすすめします。
カウンセリングの体験記事やAIとの比較記事もありますので、よければこちらも参考としてお読みください。
また、自宅で気軽に利用できる「オンラインカウンセリング」もあります。
こちらも専門家に相談できるサービスなので、気になる方にはオススメです。
薬に頼らない選択もできる
「精神科の薬はなんとなく飲むのが怖い」
「一度薬を飲み始めたら、依存してしまうんじゃないか…」
薬に関しては、私も特に大きな不安がありました。
でも実際は、薬に頼らない選択が可能でした。
私は適応障害の診断がされましたが、最初に処方されたのは少量の睡眠導入剤のみです。
この薬に常習性や依存性はないとの説明もありました。
問診表を記入する際、できれば薬に頼りたくないことを書いておいたためと思われます。
クリニックがこういったスタンスでいてくれたため、安心感がありました。
薬を出されたものの、飲むのをためらってしまうこともあるかもしれません。
もちろん症状によって薬が必要と判断されることもあると思いますが、不安であれば気持ちを抱え込まずに一度医師に相談してみると良いと思います。
悩んでいる程度では行ってはいけないと思っていた
「心療内科・精神科にかかる=心の病であることが確実」
と思っていたので、受診することのハードルがとても高く感じていました。
受診の目安がわからず、「悩んでる程度ならわざわざ診てもらうほどではないかな…」と葛藤もしました。
でも、心の問題はとても複雑で、自覚がなくても思わぬ病気が隠れていることもあります。
私も自分ではまだ大丈夫と思っていましたが、いざ診察してもらったら「適応障害」と診断されました。
早めにクリニックに行くのは大事なんだなと、身をもって実感しました。
「最近よく眠れない」「食欲がない」など、気になることがあるからちょっと相談しにいってみよう、くらいの気軽さでもいいのだと思います。
おわりに
心療内科や精神科に限らず、初めての病院に行くのは不安なことも多いと思います。
かかったことのない診療科であればなおさらですよね。
今回自分がはじめてメンタルクリニックを受診するにあたって、
「こんな情報があったらよかったな」
「前もって知りたかったな」
と思ったことをまとめてみました。
クリニックの選び方や初診の様子など、なんとなくイメージしていただけたでしょうか。
この記事を読んでいただいた方が、ご自身に合った良いメンタルクリニックと巡り会えることを願っています。
メンタルクリニックを受診するまでの、症状や気持ちの変化をまとめた記事もあります。
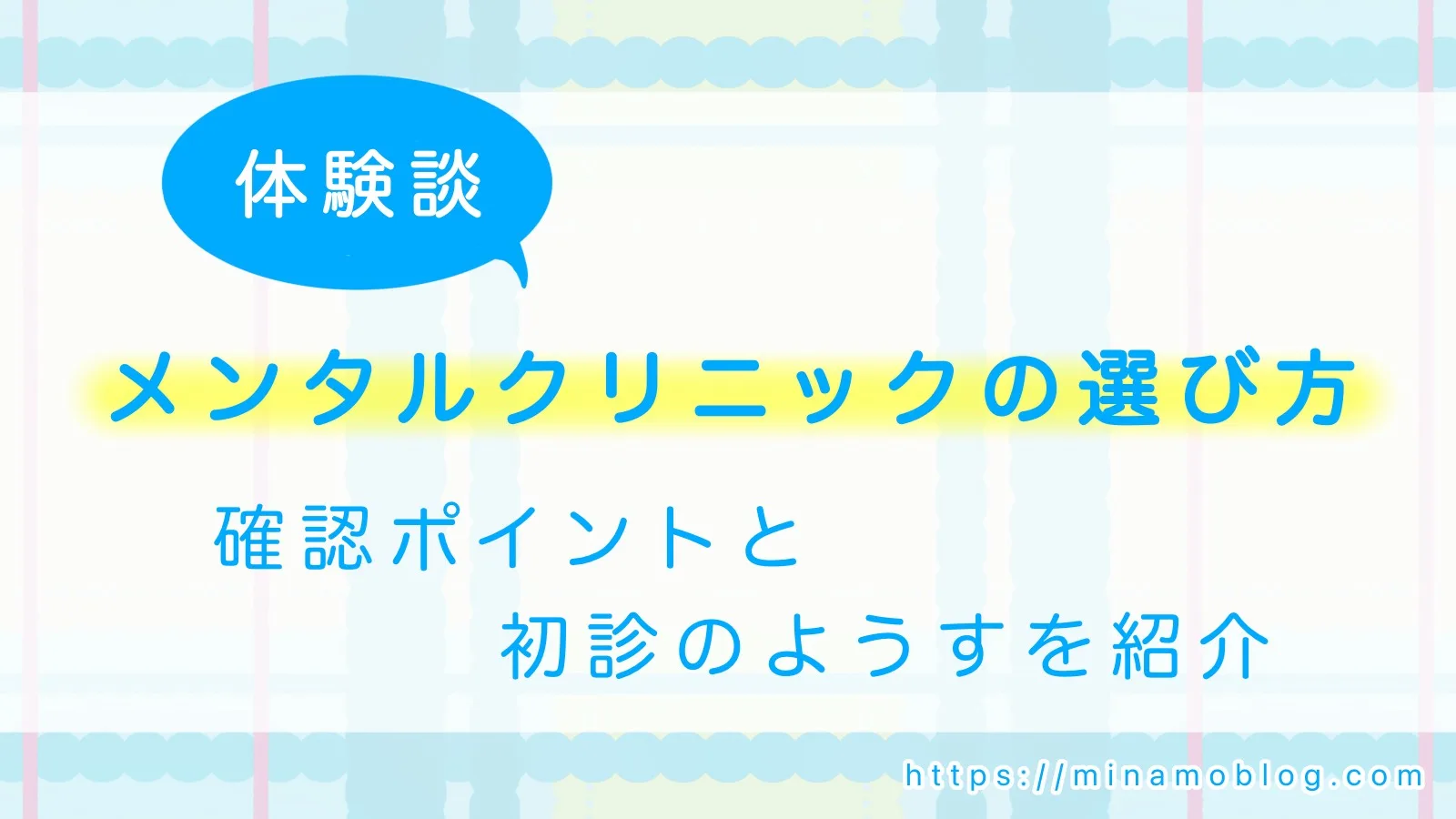
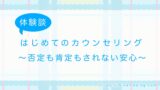
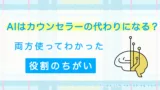
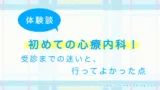
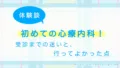
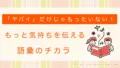
コメント