「メリバ」という言葉を、聞いたことがありますか?
メリバとは「メリーバッドエンド」の略で、ハッピーエンドやバッドエンドのように、「物語の終わり方」を表す言葉です。
ですが、このメリバという概念には、ただの物語のエンディング以上の意味が隠れています。
それは、
「何を幸せと感じるかは、自分で決めていい」
という、私たちの生き方にもつながるヒントです。
この記事では、メリバの意味や有名な作品の例をご紹介しながら、その奥にある「自分軸で生きる」という視点について探っていきます。
メリバとは? ― 言葉の意味
まずは、「メリバ」という言葉の意味について、もう少し詳しくご説明します。
メリバとは「メリーバッドエンド(Merry Bad End)」 の略で、
「merry(陽気な・幸福な)」 と 「bad end(不幸な結末)」
を組み合わせた造語です。
ネット発祥の言葉なので、聞いたことがない人もいるかと思います。
2012年頃にTwitter(現X)を中心に広まった、比較的新しい用語です。
定義があいまいなのですが、例としては以下のようなエンディングを指すことが多いです。
言葉自体は最近生まれたものですが、物語の構造そのものは、古典文学や昔話の中にも存在しています。
次の項目では、実際の物語の例を挙げながら、「メリバ」をさらに具体的に見ていきます。
有名なメリバの物語

メリバの代表例としてよく挙げられるのが、オスカー・ワイルドの童話『幸福な王子』です。
(あらすじ)
街を見下ろす王子の像は、人々の貧しさを見て心を痛め、通りがかったツバメに自分の宝石や金箔を配らせます。
王子は輝きを失い、ツバメも寒さに耐えきれず命を落とします。
みすぼらしい姿に変わった像は溶かされてしまいますが、鉛の心臓だけは残り、神様によってツバメと共に天へと導かれたのでした。
かなりコンパクトにまとめると、このようなお話です。
この物語は、どこに注目するかで印象がまるで変わってきます。
どちらが正しい、ということはありません。
「人によって解釈が分かれる」
「ハッピーともバッドとも言い切れない」
これこそが、メリバ作品に共通する魅力なのです。
他にも、メリバ的な結末の物語はたくさんあります。
どれも美しさと切なさが同居した、心に余韻を残すラストです。
ただしメリバは「見方によっては不幸」に映るため、鑑賞後の後味が良くないと感じる人も少なくありません。
「せめて物語の中くらいは幸せであってほしい」
このような気持ちは、きっと多くの人が抱く自然な感情でしょう。
けれど、メリバ作品が良くも悪くも心に残るのは、単に「悲しいから」ではありません。
それは、私たちの現実そのものが、どこかメリバ的だからではないでしょうか。
日々の暮らしのなかで、何かを諦めたり、思い通りにいかなかったりすることは誰にでもあります。
メリバ作品は、そんな「優しくない現実」を映し出す鏡のような存在といえるのです。
メリバの魅力

ではなぜ私たちは、ときにこうした「優しくない物語」に心惹かれてしまうことがあるのでしょう。
それはメリバの中に、ただ悲しいだけではない、「生きるうえでの大切な視点」が秘められているからだと思います。
ここからは、そんなメリバ作品の魅力をお伝えしていきます。
「幸せのかたちは人それぞれ」という考え方
メリバの物語には、他人の物差しに振り回されない強さが描かれています。
たとえば、先ほどご紹介した『幸福な王子』。
この物語は、よく「自己犠牲や博愛の大切さ」を説く話だと解釈されます。
でも、もう少し違う見方もできるのです。
『幸福な王子』のなかには、ツバメと王子のこのようなやりとりがあります。
ツバメは宝石を届けたあと、こう言いました。
「不思議なことですが、とても寒いのに、今はあたたかい気分です」
すると王子は答えます。
「それは君が良い行いをしたからだよ」
ここで描かれているのは、自己犠牲というより「人に貢献することで自分も満たされる」という感覚です。
心理学では、これを「他者貢献」と呼びます。
自分を犠牲にして尽くすのではなく、人の役に立つことで自分の存在価値を実感する。
評価されるかどうかは関係ないのです。
つまり王子とツバメは、「人のためでありながら、同時に自分の幸せのために行動した」と言えるのです。
『幸福な王子』は、そんな「自分軸の生き方」をそっと教えてくれている気がします。
結果より過程を大切にする
なにか行動をするとき、もちろん「結果」は大事です。
でもそれだけではなく、「過程で何を得たか」も同じくらい大切だということを、メリバの物語は教えてくれます。
たとえば『鬼滅の刃』(以下、軽いネタバレを含みます)
炭治郎は最終的に鬼の始祖・無惨を倒しますが、その道のりで多くの仲間を失います。
もし彼が「仲間を失った」という事実(=結果)だけに囚われていたら、前に進めなかったかもしれません。
けれど炭治郎は、戦いの中で仲間たちの想いに触れ、こう感じていきます。
ただ失ったのではなく、仲間と共に過ごした時間の中で深い絆を得たからこそ、最後には大きな力へと変わったのです。
これはフィクションのなかだけの話ではありません。
現実の私たちも同じように、
そんな経験を抱えながら生きています。
けれど、夢中になった時間や、共に過ごした記憶を「過程」と呼ぶのなら。
結果だけがすべてではないことは、もう十分に伝わるのではないでしょうか。
報われないけど幸せだった、私の体験談

先ほど、「現実そのものが、どこかメリバ的だ」というお話をしました。
ここからは、それをもう少し身近に感じてもらえるように、私自身の体験をひとつお話ししたいと思います。
もしよければ、参考までに読んでみてください。
10代の頃の夢は、歌手になってたくさんの人の前で歌うことでした。
ライブハウスや路上ライブ、自主制作のCD、仲間と開いたイベント。
まだ配信が主流ではなかった時代、あちこちに足を運び、人目につくために必死でした。
けれど現実は厳しく、お客さんが1人しかいないライブも当たり前。
物販のときも、隣のブースではCDがどんどん売れていくのに、自分は閑古鳥…そんな日もありました。
活動は途中で止まりつつも、合計8年続けました。
誇れる実績といえば、地方ラジオ局のコーナー曲に採用されたことくらい。
それ以外は、形に残るものは何もありません。
最終的に、私は音楽活動からは完全に引退しました。
「この8年に意味はあったのだろうか」
そんなふうに考えたことも、一度や二度ではないです。
でも、最近になって気づいたことがあります。
音楽活動での経験は、今ブログに活きているのです。
お客さんが1人でも、私は全力で歌いました。
だから今も、読んでくれる人がたとえ1人だとしても、全力で書くことができる。
こうしてあなたがいまこの記事を読んでくれていること。
それ自体が、あの頃の努力が無駄ではなかったことの証なのです。
ここまでが、私の体験談です。
「夢を諦めた」という視点で見れば、この話はバッドエンドかもしれません。
けれど実際の私は、「報われなかった努力」を糧にして、今を幸せに生きています。
それはまさに、メリバの物語そのもの。
良いこともあれば、つらいこともある。
大きな転機を迎えたとしても、人生は続いていきます。
報われることだけが、幸せの唯一の条件じゃない。
そう気づくことができれば、人生はもっと豊かに、もっと楽しくなってゆくはずです。
まとめ
今回は、「メリバ(メリーバッドエンド)」という物語の結末を手がかりに、“自分らしく幸せに生きる”ということについてお話しました。
人生は、本や映画のように一部分だけが切り取られるわけではありません。
嬉しいことも、つらいことも、すべてがつながりながら続いていきます。
だからこそ大切なのは、
人生をどう「解釈」するかは、いつだって自分にゆだねられているのです。
この記事が、あなたが「自分の軸」に気づくためのきっかけとなったら嬉しいです。
・Oscar Wilde Online(The Happy Prince)※英語サイト
・他者貢献について:嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え/岸見一郎、古賀史健(ダイヤモンド社)
↓この記事をお読みいただいた方へのオススメはこちら↓
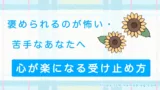
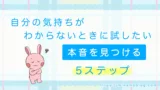
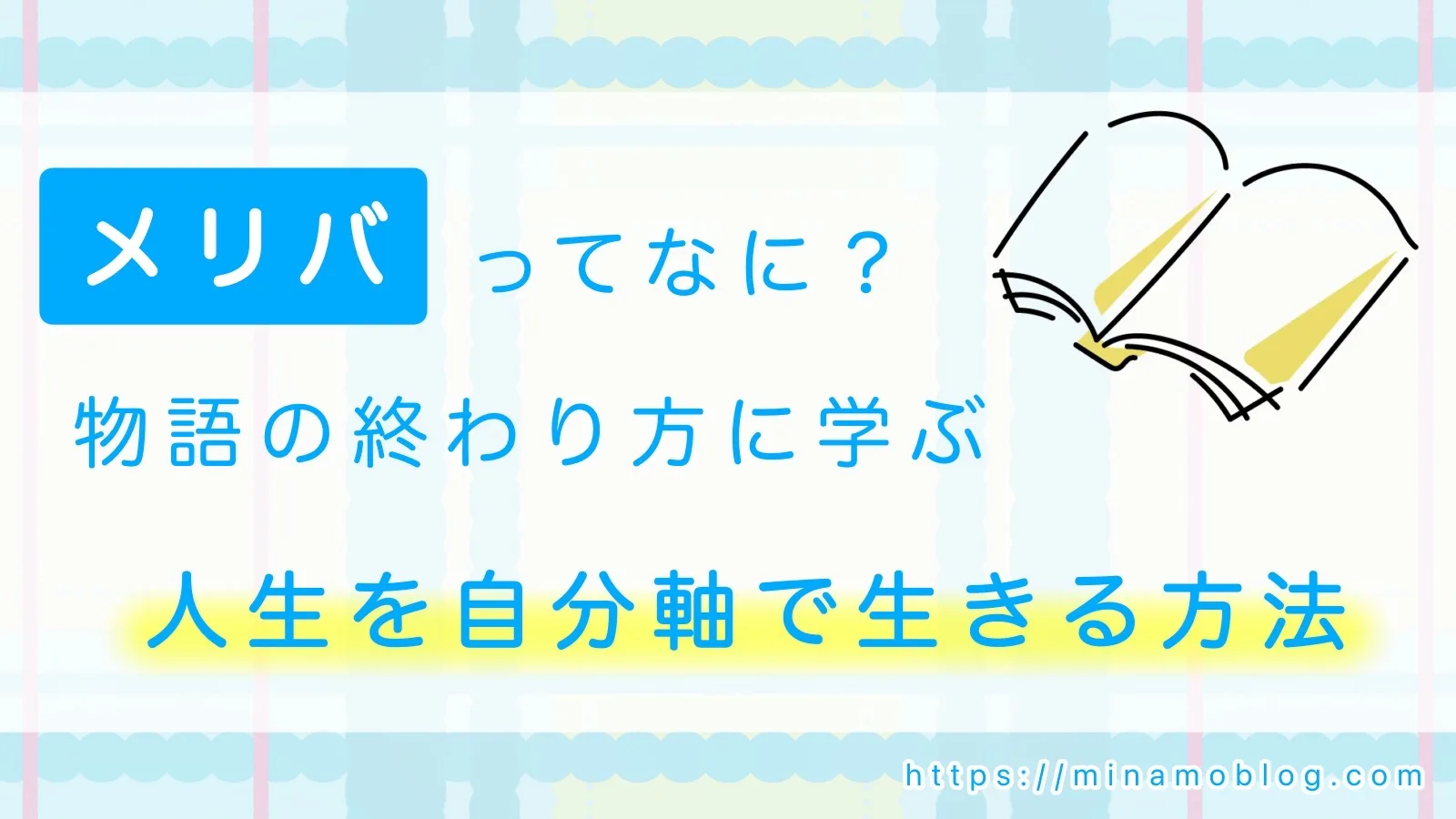
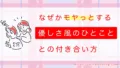
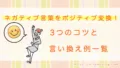
コメント